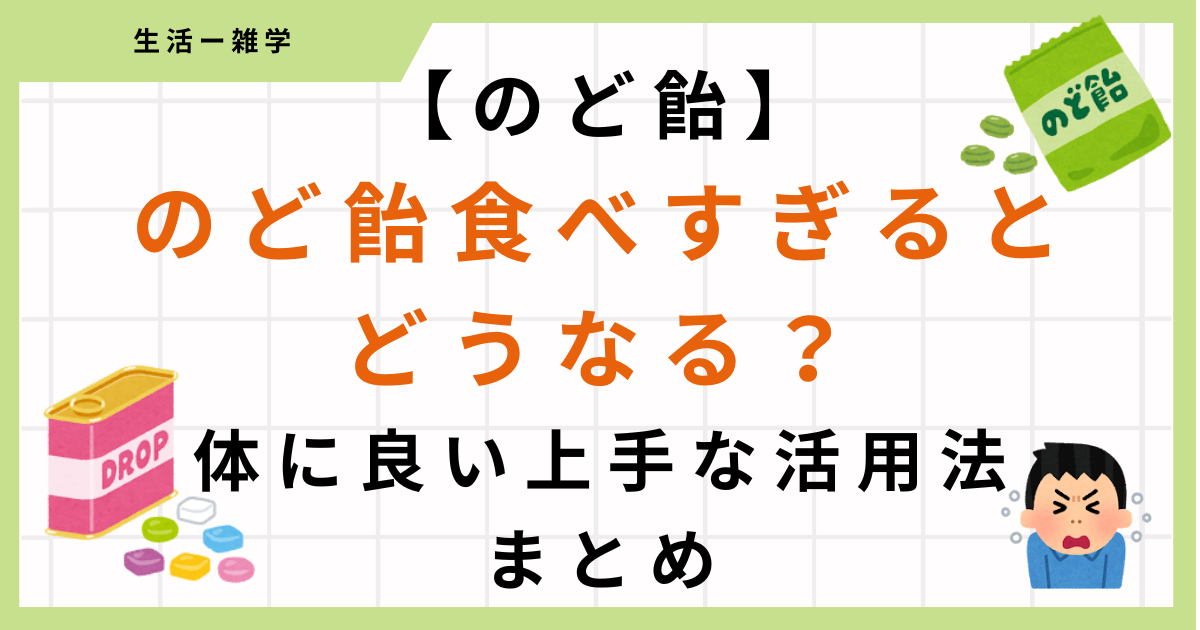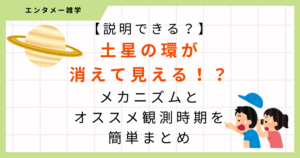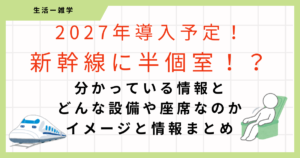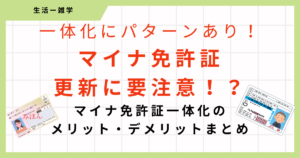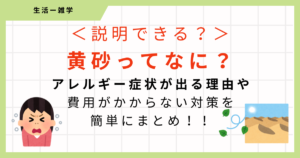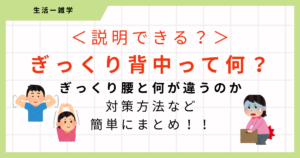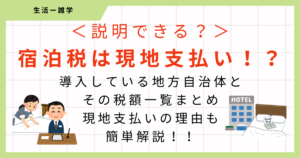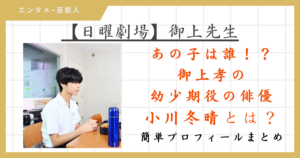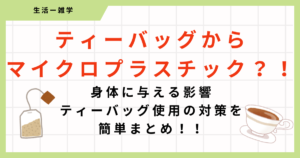空気が乾燥する冬。風邪も流行りのどがイガイガしたり、のどが乾燥したりしてあまり心地が良くないですよね。
そんな時に「のど飴」で喉をケアする人も多いでしょう。様々な種類や味も多くバリエーションが多くなっています。
 もこ丑
もこ丑ついつい何個も食べてしまいがちですよね
沢山食べても体に影響はないんでしょうか?
「のど飴」をなめ続けるとどうなるのか、体への影響と上手な「のど飴」の活用法について簡単にまとめました!
「のど飴」をなめることの有用性


「のど飴」をなめることによって、口の中を潤すことができます。
喉が不快に感じるのは、のどが乾燥してしまっているからであり、「のど飴」を食べることは適切な行動と言えます。
「のど飴」は用途によって3つに分かれている
飴でも同じですが、「のど飴」だと成分などがより「のどを潤す」のに適した成分が含まれていることが多くより良い効果が期待できます。そんな「のど飴」ですが、簡単に用途によって3つに分かれています。
医療品
「のどの痛み」等の症状がある場合に「薬」として服用するものが「医療品」の分類となる。
有効成分が配合されており、副作用の心配がある
販売されているものだと、「浅田飴」、「トローチ」等がある。
医療部外品
「医療品」ではないが、有効成分が含まれているものが「医療部外品」の分類となる。
販売されているものだと、「龍角散のど飴」、「VICKS(ヴィックス)」等がある
食品
一般的な飴とあまり遜色はなく、「お菓子の飴」が食品の「のど飴」に分類される。
のどへの効能・効果は認められておらず、味や触感を楽しむものとして様々な種類がある。
販売されているものだと、「キシリクリスタル」、「キンカンはちみつのど飴」「緑茶のど飴」等がある。
「のど飴」を食べすぎると起こる悪い影響3つ


オーラルウェルネス推進委員会という口を起点とした健康づくりを考える研究会が発表した研究によると、「のど飴」や飴をなめると出てくる最初の唾液にのどの粘膜を保護する成分があることが明らかになっています。
単発的には「のど」が潤い、免疫が上がるようです。しかし、長期的に効果が続くわけではないとされています。
「のど飴」を食べすぎた場合、どんな良くない影響が起こるのか3つまとめました。
のどの粘膜の抵抗力の低下
人間は「のど」の粘膜の「繊毛(せんもう)」という細胞が活発に動いて、「のど」への異物侵入を防ぐ役割をしています。「のど飴」を舐めることで唾液が分泌されて繊毛運動が促され、「のど」の保護に必要な成分が徐々に減少していきます。
「のど」の保護に必要な成分が減ることで、「のど」に異物やウイルスが入りやすくなってしまいます。



「のど」の繊毛の働きが「のど飴」を舐めることで徐々に低下していき免疫が低下下がるようです
のどが渇きやすくなる
「のど飴」をたくさん食べることによって、唾液が減っていき口が渇いていきます。
乾燥状態が続いてさらに「のど」を潤すために「のど飴」を食べることによってさらに悪影響をもたらす場合もあるようです。
また、のど飴を何個もなめ続けることによって唾液の質も変化していきます。
飴の糖分が唾液と混ざることにより、さらさらだった唾液がべたべたした質感になっていきます。
唾液がべたつくと、のどの潤滑性が低下して乾燥を感じたり、痰も絡みやすくなってしまいます。



のどに良いと思って食べたものが、逆に体に悪くなってしまうんですね
虫歯のリスクが上がる
「のど飴」に含まれる糖分は口の中で酸性になりますが、唾液はアルカリ性を持っており、口の中で中性となることでそのバランスを保っています。
ですが、「のど飴」を食べすぎると口の中の酸性値が高くなっていきます。そうすると高酸性の環境を好む虫歯菌が活発化し、将来的に虫歯に繋がることになります。
また、飴ということもあり糖の取りすぎによって血糖値の上昇をもたらす危険性もあります。



何事もほどほどが良いということですね
「のど飴」を有効活用するために
のどには「加湿」が重要となります。
のどを乾燥させないためには、「常に加湿をする」ことが重要となります。
私たちにできることは以下の通りです。
・「のど」を潤すため、こまめに水分を取る
・マスクをつけて「のど」の乾燥を防ぐ
・自分に合った「のど飴」の個数やペースを把握する
水分を取って、「のど」を潤しマスクをつけることで口内の加湿を助ける。
そして、自分が「心地いい」と感じる「のど飴」の個数を把握して適切に利用することが、より効果的に利用ができます。



「のど飴」は嗜好品のため
「おいしい」と感じることが大切です!
まとめ
・「のど飴」はノドを潤すための第一歩として有用
・「のど飴」は食べすぎると逆に喉に悪い
・「のど飴」は個人に合った適量を摂取するのが一番良い
「のど飴」は適量を食べれば、体にとても良いものとなります。一日にどれだけの数が自分に合っているのか探して
決めておくのが大切になります。
適度に「おいしく」食べて「のど飴」を有効活用して、乾燥がまだまだ続く厳しい冬を健康に元気に乗り切りましょう!!